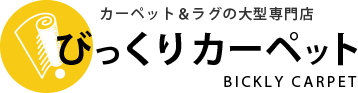梅雨に入る前にカーペットの湿気対策は万全ですか?
梅雨になると湿気が多く部屋の中に居てもジメジメしますよね。
カーペットが湿気を多く吸収すると独特の嫌な臭いが発生したり、カビが繁殖することがあります。
それだけじゃありません。
カーペットにカビが繁殖すると、フローリングや畳にカビが移ってしまうことだってあります。
フローリングや畳にカビが繁殖すると床材を全て張り替えなくてはならないケースも…。
そこで、梅雨の湿気でカーペットにカビが繁殖しないようにするために、カーペットの湿気対策と部屋の除湿方法について解説しますね!
目次
湿気の多い時期と湿気が多いと起こるトラブル

日本には四季があり、季節ごとに自然環境の変化を楽しめるというのは日本の魅力のひとつです。
一方で日本は年間を通して降水量が多く、梅雨の5月~7月は湿気で多くの人が悩まされます。
湿気が多いと屋外だけでなく屋内でも空気がジメジメして不快に感じますよね。
そして、屋内の湿度が高くなると「部屋でカビが大繁殖」、「ダニの大量発生」、「湿気を帯びた独特の嫌な臭いが部屋に充満」などの悪い影響が出ます。
特にカビは人体に悪影響を与える危険があり、小さなお子さんがいるご家庭では子供の喘息の原因となることがあります。
カビの繁殖しやすい環境は、湿度が80%以上で気温が20℃~30度といわれています。
梅雨から夏にかけての屋内はカビが繁殖しやすい非常に危険な環境になっています。
たかが湿気と甘くみていると、気づいたときにはカーペットとフローリングにカビが発生してしまっていることも…。
家をカビだらけにしないためにも、カーペットの湿気を除去して、お部屋の除湿を行う必要があります。
梅雨に備えてカーペットの湿気対策

それでは、梅雨に備えてカーペットの湿気対策にもなる除湿方法を解説したいと思います。
除湿方法にはいくつか方法があります。
- 窓を開けて部屋を換気する
- エアコンや除湿器で部屋の除湿をする
- 部屋に除湿剤を置く
- 除湿シートをカーペットの下に敷く
- カーペットを干す
手軽にできる除湿方法から、事前に準備が必要な除湿方法まで、どうやってカーペットとお部屋の除湿を行うのか詳しく解説します。
窓を開けて部屋を換気する

まずは、湿気対策の基本でもある部屋の換気を行いましょう。
換気をすることで部屋の風通しを良くして、部屋に溜まった湿気を外に逃がします。
換気が必要な場所
- リビング
- 寝室
- キッチン
- お風呂場
- お手洗い周辺
特に、水廻りのキッチン・お風呂場・お手洗い周辺は湿気が溜まりやすいので常に換気を心がけてください。
そして、意外と忘れられがちな寝室の換気が大切です。
人は汗をかくことで体温調節を行っています。
気温の高い梅雨や夏場は寝ているときに大量の汗をかきます。
その汗がシーツや布団に移って気化することで、寝室の湿度が高くなります。
それに、寝るとき窓とカーテンを閉め切っている方は、梅雨のジメジメした空気が寝室に残ってしまうので日中に窓を開けて換気を行ってください。
窓を開けて換気が難しいなら、キッチンやお風呂場の換気扇を数時間付けっぱなしにしておくだけでも換気効果があります。

梅雨の雨が降っている日でも窓を開けて換気することで一定の換気効果があります。雨の日でも窓を開けた換気をしましょう。
エアコンや除湿器で部屋の除湿をする

エアコンを除湿運転で点けてお部屋を除湿したり、除湿器で除湿する方法があります。
エアコンはご家庭に広く普及しているので、除湿方法としては簡単な方法になります。
ただし、エアコンの除湿機能の種類には注意が必要です。
エアコンの除湿機能には、「弱冷房除湿」と「再熱除湿」の2種類があります。
・弱冷房除湿
弱冷房除湿は湿度を一定値まで下げるために弱い冷房運転を続けます。
・再熱除湿
再熱除湿は室内機内で部屋の空気を取り込んで冷やして除湿します。
梅雨の低温多湿では「再熱除湿」が向いているといわれていますが、再熱除湿は弱冷房除湿より消費電力が多いというデメリットがあります。
そのため、梅雨にエアコンを使った除湿は効率は良いが電気料金が高くなる傾向にあります。
エアコンを使って除湿する場合は、ご自宅のエアコンが「弱冷房除湿」と「再熱除湿」どちらの除湿機能なのか確かめてから使ってください。
でないと、想像していた以上の電気料金の請求額を見てビックリすることになります。
除湿器を使った除湿

梅雨にエアコンを使った除湿はコスト高になりやすいので、除湿器でお部屋の除湿を行うという方法もあります。
除湿器には3つのタイプがあります。
・コンプレッサー方式
除湿器内部で空気を冷やして結露を発生させて除湿する。
・デシカント方式
除湿器内部のヒーターで空気を温めて除湿する。
・ハイブリット方式
ハイブリット方式は、コンプレッサー方式とデシカント方式を合体させた除湿器です。
除湿器はエアコンよりも消費電力が少なく、カーペットのあるリビングや寝室などに持ち運ぶことができるというメリットがあります。
デシカント方式やハイブリット方式は空気を温めて除湿するのでオールシーズンで使用することができます。
でも、梅雨から夏にかけて使うならコンプレッサー方式がおすすめです。
除湿器はエアコンと比べて消費電力が少なく、その中でもコンプレッサー方式の消費電力は150W~240Wと3つの中でも低い値です。
また、除湿器の価格は比較的に価格の安いコンプレッサー方式の除湿器で10,000円~20,000円、ハイブリット方式の除湿器で30,000円~50,000円です。
ただ、除湿と空気清浄機能が一体になっている物もあるため本体価格が10万円を超える高価な物もあります。
家電量販店などで除湿器や除湿機能付きの空気清浄機の実物を確認してから購入することをおすすめします。
部屋に除湿剤を置く
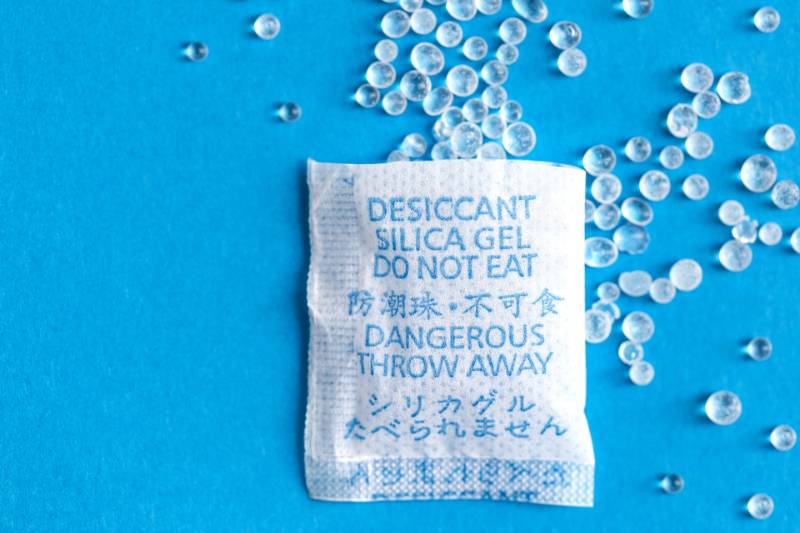
エアコンや除湿器よりも即効性は低くなりますが、お部屋に除湿剤を置いて除湿する方法があります。
除湿剤といえば、タンスやクローゼットの除湿に使われる物を思い浮かべますが、カーペットのあるお部屋に置いて除湿に使うこともできます。
お部屋に置くタイプの除湿剤はボックス型の据え置きタイプが一般的です。
この除湿剤の中に入っている薬剤は3種類ありますが、それぞれ除湿効果に違いがあります。
| 除湿剤 | 除湿効果 |
| 塩化カルシウム | 除湿効果が高い。 |
| シリカゲルA型 | 塩化カルシウムと同程度の除湿効果がある。 |
| シリカゲルB型 | 他2つの除湿剤より除湿効果が低い。 |
塩化カルシウムを使った除湿剤が最も除湿効果が高くなります。
お部屋の除湿に除湿剤を使う場合、除湿剤を置く場所に注意してください。
湿気は地面に近い場所に溜まりやすいという性質があるので、床に近い場所に除湿剤を置くと高い除湿効果を得られます。
ただし、除湿剤を使うときの注意点として、除湿効果の高い塩化カルシウムは人体に触れると肌が炎症を起こすなど悪影響があります。
小さなお子さんや犬猫等のペットと一緒に暮らすご家庭では、塩化カルシウムではなく人体への影響の少ないシリカゲルを使ったほうが良い場合もあります。

カーペットの側に除湿剤を置くときは、子供やペットが除湿剤に触れないように注意して使ってくださいね!
除湿シートをカーペットの下に敷く

カーペットの裏側に湿気が溜まらないように除湿シートを敷いて梅雨の湿気対策にすることができます。
除湿シートにもいろんな種類がありますが、その中でもおすすめなのが「洗濯可能な除湿シート」です。
洗濯できる除湿シートの素材
- モイスファイン
- モイスファインEX
- アクティブレス
除湿シートに使われる素材はいくつか種類があり、洗濯できる物と出来ない物があります。
ここで挙げた3つの素材を使った除湿シートは洗濯ができるので、定期的に除湿シートを洗濯機で洗って清潔な状態で使用することができます。
ただ、洗濯可能な除湿シートにもデメリットがあります。
それは洗濯可能な除湿シートは他の除湿シートと比べて高価というデメリットがあります。
メーカーにもよりますが、3,000円~6000円ほどの価格になります。
シリカゲルの除湿シートが1,000円ほどなので、コスト面を優先するならシリカゲルなど低価格の除湿シートを使うことも考えましょう。

最近は珪藻土を配合したタイプの除湿シートも売られています。吸湿性の高い珪藻土を使った除湿シートは性能も高く人気があります。
カーペットを干す

カーペットは敷きっぱなしにせず、定期的にカーペットを干しましょう。
年間を通してカーペットは敷きっぱなしにしている、というご家庭ではカーペットの裏側に湿気が溜まりやすくなっています。
カーペットの裏側に湿気が溜まると、カーペットにカビが繁殖するだけでなく、カーペットに接触しているフローリングや畳にカビが移ってしまう危険があります。
そのため、カーペットの湿気対策に「陰干し」をしましょう。
太陽の光が直接当たらない風通しの良い場所でカーペットを裏返して干してください。
陰干しをすることで、湿気の溜まったカーペットを乾燥させることができます。
ただ、ご自宅に大きなカーペットを陰干しするスペースが無かったり、梅雨で雨の日が続いて屋外にカーペットを陰干しするのが難しい場合もあると思います。
その場合は、お部屋の床でカーペットを半分ずつめくって換気をするだけでも除湿効果があります。
家具の下に敷き込んだカーペットを乾燥させる
ご家庭によってはカーペットを家具の下まで敷き込んで使っている場合もあると思います。
そのような場合は、家具の下に敷いたカーペットの一部でカビが繁殖することがあります。
家具を移動させて、家具が置かれていたカーペットの一部を乾燥させるようにしてください。
でも、敷き込んで使っているカーペットは干すのが難しいですよね?
カーペットの陰干しが難しい場合は、窓を開けて換気をすると同時にサーキュレーターや扇風機を使って空気の循環を良くすると換気効果を高くすることができます。
また、定期的にカーペットの上に乗せた家具を移動させて、湿気が溜まらないようにしましょうね!
カーペットのカビ・臭い対策

湿気対策に換気や除湿シートを使っていても、カーペットからカビや嫌な臭いが発生することがあります。
普段の洗濯やお掃除に使う日用品でカーペットのカビと嫌な臭いの対策をしましょう!
カーペットの定期的なお手入れ

カビが繁殖しやすい環境は湿度が80%以上で気温が20℃~30℃の環境というのは解説しました。
この条件の他にカビが繁殖する要因として、カーペットに付着した汚れ(ホコリや食べこぼし)をそのままにしておくとカビが繁殖しやすくなります。
そのため、カーペットのお手入れは定期的に行ってください。
お手入れの方法は、粘着クリーナーや掃除機でカーペット表面に付着しているホコリや髪の毛を取ります。
汚れが酷い場合は、手洗いや洗濯機で洗浄しましょう。
水洗いが難しい床に敷き込んで使っているカーペットには、カーペットクリーナー等の専用洗剤を使って汚れを落とします。
ホコリや食べこぼしが残っているとカビだけでなくダニの発生にもつながります。
定期的にカーペットをお手入れして、ホコリや食べこぼしをそのままにしないように心がけてください。
カーペットのお手入れ方法について詳しく解説しているのでこちらの記事も参考にしてください。
また、水洗い出来ないカーペットでも使える洗剤には水を使わないカーペットシャンプーがおすすめです。
除菌・消臭スプレーで対策

梅雨の湿気でカーペットから嫌な臭いがしてくるのを防ぐ方法として除菌・消臭スプレーを使います。
除菌・消臭スプレーは様々な種類が販売されていますが、無香料の除菌・消臭スプレーがおすすめです。
湿気による嫌な臭いは、洗濯物を部屋干しした時に感じる臭いと似ています。
この湿気による嫌な臭いはニオイ菌などの細菌が原因です。
カーペットを除菌することで、嫌な臭いの消臭からカビ菌を殺菌することができます。
この除菌・消臭スプレーにも種類があります。
| アルコール除菌消臭スプレー | エタノールが配合されたスプレーで家具などの除菌にも使える。発揮性が高く除湿の効果が多少ある。 |
| 自然成分除菌消臭スプレー | 天然由来の除菌成分を配合したスプレー。ヒノキやオレンジ、グレープフルーツなどに含まれる除菌成分を抽出した物。 |
| 塩素系除菌スプレー | 次亜塩素酸系の化学成分が含まれた除菌スプレー。除菌だけでなく漂白効果も期待できる。 |
よく知られる除菌・消臭スプレーの中でも「アルコール除菌消臭スプレー」が有名です。
アルコール成分は人体への影響も少なく、カーペットやラグに使用することができます。
また、除菌・消臭スプレーの中には香料の付いたスプレーがありますが、香料ありのスプレーはあまりおすすめできません。
何故なら、カーペットから感じる嫌な臭いを他の強い臭いで誤魔化すだけなので、嫌な臭い自体が無くなったわけではありません。
それに、強い香料は人体に影響がなくても、犬猫等のペットには刺激が強く悪影響を及ぼす危険があります。
人体やペットへの影響を考えると塩素系除菌スプレーもカーペットには使わないほうがいいでしょう。

塩素系除菌スプレーはカーペットやラグに使うと色落ちしてしまう危険があるので色付きのカーペット・ラグには使わないようにしてくださいね!
重曹でカーペットの除湿・洗浄

人体や動物に悪影響が少ない重曹を使ってカーペットの湿気を取り、汚れを落とすことができます。
重曹は「ベーキングソーダ/baking soda」とも呼ばれ、化学名は炭酸水素ナトリウム、私たちの身近な物だと料理に使う膨らし粉があります。
この重曹はお掃除で頑固な油汚れを落とすときに洗剤の代わりとして使われます。
そして、重曹の特徴として人間の汗に含まれるアンモニア臭を中和する効果と、空気中の水分を吸収する除湿効果があります。
湿気の多い梅雨に、カーペットの上に重曹を撒いてしばらく放置(2時間~3時間ほど)してから、掃除機でカーペットの重曹を吸い取るだけでカーペットの消臭と除湿を同時に行うことができるのです。
重曹を使ったお手入れ方法については過去に詳しく解説しているのでそちらもご確認ください。
湿気の多い梅雨におすすめのカーペット
それでは、湿気の多い梅雨におすすめのカーペットをご紹介したいと思います。
梅雨から夏にかけてカーペットを代えようと考えている方は是非参考にしてみてくださいね!
吸湿性に優れたウールのカーペット

梅雨の湿気が多い時期は、吸湿性に優れたウールのカーペットをおすすめします。
ウールの特性に湿気を吸収発散しやすいというのがあります。
湿気を含んだとしても、部屋の除湿をしっかり行うことで十分乾燥させることができます。
また、ウールは冷感性にも優れるという特徴があるので、湿気でジメジメしていてもカーペットが肌に張り付くような嫌な感じが少なく、梅雨でも快適に過ごすことができます。
ウール製のカーペットを選ぶときは、撥水と防カビ・防虫加工がされたウールカーペットを選ぶのがおすすめです。
通気性と吸湿発散に優れたい草・麻混カーペット

梅雨から夏にかけて部屋で涼しく過ごすならい草・麻混のカーペットがおすすめです。
見た目も夏らしく涼しげな雰囲気のい草カーペットは日本の夏にピッタリです!
い草には抗菌効果があるので、カビが発生しにくく、その他の細菌にも強いという特徴があります。
夏場の心配といえば汗などによる汚れで細菌がカーペットの上で繁殖してしまうことですが、い草カーペットならい草自体の抗菌効果である程度防いでくれます。
い草カーペットの他に、麻混のカーペットは手触りもよく肌に当たる感触がやわらかいので、夏場のリビングで気持ちよく体を横にすることができます。
カビが付きにくいナイロン・ポリエステルのカーペット

お手入れが簡単でカビ・ダニが繁殖しにくいナイロン・ポリエステルのカーペットも梅雨におすすめです。
化学繊維はダニ・カビが繁殖しにくいという特徴があるだけでなく、防カビ・防虫・抗菌加工を施すことで湿気の多い時期に必要な機能が備わっています。
ナイロンやポリエステルなどの化学繊維は耐久性に優れていて、洗濯機で丸洗いできるカーペットもあります。
ただ、全ての化学繊維のカーペットが洗濯機で丸洗いできるわけではないので、洗濯できるタイプのカーペットを選びましょう。
また、カーペットを洗濯する前に必ず洗濯表示の確認をしてから洗濯するようにしてくださいね。
ウール・ムートンのカーペットはカビやダニが発生しやすい?

ウールやムートンなどの羊毛を原料としているカーペットにはカビやダニが発生しやすい、という話を聞いたことがあると思います。
確かに、他の化学繊維などと比べてウールやムートンで織られたカーペットはダニやカビが発生する危険が多少高くなります。
ただ、ウールやムートンが特にダニやカビが発生しやすいというわけでなく天然繊維で織られたカーペットは、化学繊維で織られたカーペットよりダニやカビが多少発生しやすいという程度です。
| ダニ・カビが発生しやすいカーペット | ウール・ムートン・シルク・レザー・リネン・コットンなど |
| ダニ・カビが発生しにくいカーペット | ナイロン・ポリエステル・アクリル・ポリプロピレンなど |
また、天然繊維の中でもカビ・ダニが付きにくい物もあります。
例えば、シルクやレザーなど天然繊維でも動物性の物にはカビやダニが発生しやすく、リネンやコットンはそれより若干カビやダニが発生しにくい程度の違いがあります。
ウールやムートンは、繊維や生地として保湿効果があるのに冷感効果も高く、湿気を良く弾き吸湿性が高いという大変優秀な繊維でもあります。
そのため、ウールやムートンで織られたカーペットは冬はもちろん夏でも人気があります。
ダニ・カビが発生しやすいというのも、日頃のお手入れと湿気の多い梅雨はしっかり除湿を行うことで十分防ぐことができます。
ですから、湿気の多い梅雨の時期にウールやムートンのカーペットを使うなら、お手入れと除湿を忘れずに行えば、ダニ・カビの発生を防いでウール・ムートンのカーペットを使用していただけます。

ウールやムートンは「ウールの七不思議」と呼ばれる優秀な特徴があります。
「高い撥水性と吸湿性」、「高い保湿・冷感効果」、「型崩れしにくい」、「延焼しにくい」、「色落ちしない」、「汚れが付きづらい」、「フェルト化」
カーペットや床にカビが発生してしまったら

カーペットや床にカビが発生しないように対策をとっても、カビが発生してしまうことがありますよね。
そのような場合は、カーペットと床を洗浄してカビ取りをする必要があります。
カーペットや床のカビ取りは「自分で洗う」か「クリーニングで洗ってもらう」という方法があります。
自分で洗う場合、カーペットと床を塩素系の洗剤で洗うことでカビ取りを行います。
ただし、塩素系の洗剤はカーペットが脱色したり、フローリング材に塗付されたワックスを剥がしてしまう危険があります。
カビに浸食されている範囲が狭い場合は、自分でカビ取りを行うこともできますが、カビの範囲が広い場合は専門業者に依頼するのも手段の一つです。
ハウスクリーニング業者なら、カビが付いたカーペットと床の両方を洗浄してくれます。
または、カビがカーペットだけに付いていた場合は、クリーニング店にカーペットの洗浄を依頼することもできます。
カーペットや床にできてしまったカビの洗浄は簡単ではありません。
カビ取りが難しいと感じたら、ハウスクリーニングなどの専門業者に相談しましょう。
自分でカビ取りをする詳しい方法は過去の記事で紹介しているので、こちらの記事を参考にしてください。
湿気が多い家の特徴

カーペットと部屋の除湿について解説してきましたが、暮らしている家の中にはもともと湿気が多い家もあります。
日本の気候は多湿なので、ある程度の湿気は仕方がありませんが、季節に関係なく湿気の多い家には問題があります。
湿気の多い家の特徴
- マンションの1階
- 日当たりと風通しが悪い
- 土地が他の土地よりも低い場所にある
- 雨漏りや水漏れがある
- 過去に田んぼや湿地だった
マンションの1階は湿気が多いという話は耳にしたことがあるかもしれません。
マンションの1階は同じマンションの他の階と比べて地面からの湿気を取り込みやすいという特徴があります。
他にも戸建ての住居では、その土地が過去に田んぼや湿地跡だった、河川や他の土地よりも低い土地に建てた住居は湿気が溜まりやすくなります。
また、最近は鉄筋コンクリートなど建物の構造的に風通しが悪くて湿気が溜まりやすい家もあります。
このような特徴を持つ家は、ここで解説した湿気対策でお部屋を除湿できる場合もありますが、構造上の理由から除湿が難しい場合もあります。
湿気が多い家では、カビ以外にも白アリ被害や建材の腐食などの大きな問題が発生している可能性があります。
除湿対策をしても部屋がジメジメしている、床のフローリングがグニグニして凹むなどしたら、はやめに専門業者へ相談したほうがいいでしょう。
まとめ
梅雨の湿気でカーペットがカビてしまうのは珍しいことではないので「仕方がない」と諦めていませんか?
正しく対策をすれば、カーペットやフローリングのカビを予防することはできます。
自宅の部屋でどこが一番湿気が多いのか、効果的に除湿をする方法を知ることで、カビの繁殖や梅雨の嫌な臭いをやわらげることができます。
除湿器や除湿剤を置く以外にも部屋の換気を定期的に行い、湿気の溜まりやすいキッチンやお風呂場は特に注意して乾燥するように心がけましょう。
梅雨前にお部屋の除湿対策をしっかりやっておけば、湿気の多い梅雨で気持ちよくカーペットを使うことができるので、ここで解説した湿気対策を試してみてくださいね!